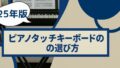「ピアノを始めてみたいけど、いきなり本物のピアノはハードルが高い…」
「練習用に、ピアノに近いタッチのキーボードが欲しい!」
そんなピアノ初心者の方の思いに応える選択肢として、「ピアノタッチキーボード」は近年非常に人気があります。自宅で気軽に始められ、本格的なピアノ演奏の基礎を学ぶことができる優れたアイテムです。しかし、様々なモデルが存在するため、何も知らずに選んでしまうと「思ったのと違った…」と後悔してしまうことも。
この記事では、ピアノ初心者の方が自分に最適なピアノタッチキーボードを選び、後悔なくピアノ練習をスタートできるよう、選び方の重要ポイントを5つに絞って詳しく解説します。各ポイントの意味や、なぜそれが大切なのかを理解し、納得の一台を見つけるための羅針盤としてご活用ください。

ピアノ指導歴20年の経験からピアノタッチキーボードの選び方と
オススメのキーボードを紹介します!

アコースティックピアノ 
電子ピアノ
ピアノタッチキーボード
- 「ピアノタッチキーボード」とは?普通のキーボードとの違いを理解しよう!
- ピアノタッチキーボード選びで失敗しない!5つのチェックポイント
- ピアノ講師オススメのピアノタッチキーボード|電子ピアノ
- アコースティックピアノに近いオススメのサスティンペダル
- ぜひ試奏を! – 百聞は一見に如かず、百見は一触に如かず
- 主なメーカーとその特徴
- まとめ:自分に合った一台で、楽しいピアノライフを始めよう!
「ピアノタッチキーボード」とは?普通のキーボードとの違いを理解しよう!
まず、ピアノ選びの第一歩として、「ピアノタッチキーボード」がどのようなものか、そして安価なキーボードとは何が決定的に違うのかを明確に理解しておくことが重要です。この違いを知ることで、なぜピアノの練習にピアノタッチが推奨されるのかが分かります。
ピアノタッチキーボード(電子ピアノのエントリーモデル含む)
特徴1:鍵盤に「重さ」があること
アコースティックピアノの鍵盤は、ハンマーアクションという仕組みによって、押したときにしっかりとした手応えがあります。ピアノタッチキーボードはこの感覚を再現しており、鍵盤にある程度の「重さ」がつけられています。この重さによって、正しい指の形や力加減を養い、ピアノを弾くための基本的な指の力を鍛えることができます。豊かな表現力を身につけるための土台作りと言えるでしょう。
特徴2:タッチレスポンス機能の搭載
ピアノの魅力は、弾く力の強弱によって音の大きさや音色を変化させられる表現力にあります。ピアノタッチキーボードには、この力の強弱を感知して音量を変える「タッチレスポンス」機能が搭載されています。これにより、ppp(ピアニッシッシモ:極めて弱く)からfff(フォルティッシッシモ:極めて強く)までのダイナミクス(強弱)を意識した練習が可能になり、音楽的な表現力を学ぶ上で欠かせません。
特徴3:ピアノに近い鍵盤数(主に88鍵)
多くのピアノ曲は、アコースティックピアノの標準である88個の鍵盤を前提として書かれています。ピアノタッチキーボードの多くは、この88鍵を備えており、演奏できる曲の幅が広く、本格的なピアノ曲にも対応できます。
普通のキーボード(安価なもの)
❌軽い鍵盤タッチ
安価なキーボードの多くは、鍵盤が非常に軽く、指で押してもほとんど抵抗がありません。これは持ち運びや簡単なメロディ演奏には便利ですが、ピアノ演奏に必要な指の力を養うには不向きです。軽いタッチに慣れてしまうと、本物のピアノを弾いたときに指が疲れてしまったり、うまくコントロールできなかったりする可能性があります。
❌タッチレスポンスがない、または簡易的
安価なモデルでは、タッチレスポンス機能が搭載されていない、あるいは搭載されていても感度が低い場合があります。これでは、どれだけ強く弾いても弱く弾いても同じ音量しか出ず、ピアノならではの表現豊かな演奏を学ぶことが困難になります。
❌少ない鍵盤数(61鍵など)
鍵盤数が61鍵などのモデルが多く、これはピアノ曲を弾くには音域が足りません。弾きたい曲の楽譜を見ても、必要な音が出せないという場面にすぐ直面してしまいます。
ピアノの上達を真剣に考えるのであれば、鍵盤の重さ、タッチレスポンス、鍵盤数を備えた(理想は88鍵盤少なくとも76鍵盤)「ピアノタッチ」のキーボードを選ぶことが、遠回りのようで実は最も効果的な練習への近道となります。

具体的な選び方を説明します!
ピアノタッチキーボード選びで失敗しない!5つのチェックポイント
では、数あるピアノタッチキーボードの中から、自分に合った一台を見つけるためには、具体的にどこに注目すれば良いのでしょうか?以下の5つのポイントは、購入前に必ずチェックしておきたい重要な要素です。それぞれのポイントがなぜ大切なのか、理由と共に見ていきましょう。
1. 鍵盤のタッチ感(最重要!)- 指先の感覚を確かめよう
ピアノタッチキーボードを選ぶ上で、最も重要と言っても過言ではないのが「鍵盤のタッチ感」です。なぜなら、指先の感覚はピアノ演奏の基本であり、練習の質、ひいては上達のスピードに直結するからです。不自然なタッチのキーボードで練習を続けると、変な癖がついてしまう可能性もあります。
「重さ」を感じるか?
店頭などで試奏する際、まず確認したいのは、鍵盤を押したときにしっかりとした「重さ」や「手応え」があるかどうかです。軽いタッチのキーボードとは明らかに違う、指にしっかりとした抵抗を感じられることがピアノタッチの基本です。この重さが、ピアノを弾くための指の筋力を自然に鍛えてくれます。
よりリアルさを求めるなら「グレードハンマー」
アコースティックピアノの鍵盤は、実は全ての鍵盤が同じ重さではありません。低音域の弦は太く長いため、それを叩くハンマーも大きく重くなり、結果として低音部の鍵盤は重くなります。逆に高音域は弦が細く短いため、ハンマーも軽く、鍵盤も軽くなっています。この「低音域は重く、高音域は軽い」という段階的な重さの変化を再現したのが「グレードハンマー」機能です。(メーカーにより「グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤」「レスポンシブ・ハンマー・アクション(RHA)鍵盤」など呼称が異なります)。より自然なピアノの感覚で練習したい場合は、この機能の有無をチェックしましょう。タッチ感がより本物のピアノに近づきます。
表現力の要「タッチレスポンス」
前述の通り、弾く力の強弱によって音量が変わる機能です。これにより、メロディを際立たせたり、感情を込めた演奏をしたりすることが可能になります。ピアノタッチを謳うモデルには基本的に搭載されていますが、念のため仕様を確認しましょう。機種によっては、自分のタッチの癖に合わせて感度を数段階で調整できるものもあり、より細やかな表現が可能になります。
タッチ感は、カタログのスペックだけでは判断が難しい部分です。感じ方には個人差もあります。可能であれば、必ず楽器店に足を運び、複数のメーカーや価格帯のモデルを実際に弾き比べてみてください。 少しの時間でも、指先の感覚を確かめることで、自分にとって「しっくりくる」タッチを見つけやすくなります。
2. 鍵盤数 – 弾きたい曲が弾けるか?
次に重要なのが鍵盤の数です。これが少ないと、せっかく練習しても弾ける曲が限られてしまい、モチベーションの低下にも繋がります。
理想はやっぱり「88鍵」
アコースティックピアノ、グランドピアノ、アップライトピアノの標準的な鍵盤数は「88」です。クラシックの名曲から最新のJ-POP、映画音楽まで、世の中のほとんどのピアノ曲はこの88鍵の音域を前提に作られています。 長くピアノを楽しみたい、様々な曲に挑戦したいと考えているなら、最初から88鍵のモデルを選ぶのが最も合理的です。後から「この曲、鍵盤が足りなくて弾けない…」となる心配がありません。
スペースや予算で妥協するなら「76鍵」や「73鍵」
どうしても設置スペースが限られている、あるいは予算を抑えたいという場合には、76鍵や73鍵のモデルも選択肢に入ります。ポピュラー音楽や比較的音域の狭い曲を中心に楽しむのであれば、これらの鍵盤数でもある程度対応可能です。しかし、クラシック曲、特にロマン派以降の作品などでは、最高音や最低音が足りなくなる場面が出てくる可能性があります。自分の弾きたいジャンルを考慮して選びましょう。
「61鍵」はピアノ練習には基本的に不向き
入門用の安価なキーボードに多い61鍵ですが、これはピアノの代わりとして考えるのは難しいでしょう。両手で和音を弾いたり、広い音域を使ったりするピアノ曲の練習には、明らかに鍵盤数が不足します。「ドレミファソ…」と単音でメロディを追う程度なら可能ですが、本格的なピアノ練習には適していません。
3. 音質(ピアノの音)- 練習のモチベーションを左右する
鍵盤のタッチ感と並んで、練習を楽しく続けられるかどうかに関わるのが「音質」です。特に、メインとなるピアノの音が心地よいかどうかは非常に重要です。
リアルで心地よいピアノ音源か?
ピアノタッチキーボードは、内蔵された音源によって音を出しています。この音源の質が低いと、せっかく練習しても電子的な響きが気になり、演奏への没入感が損なわれてしまいます。特にアコースティックピアノの豊かで深みのある響きをどれだけ再現できているかは重要なポイントです。これも可能であれば試奏時に、内蔵スピーカーとヘッドホンの両方で、様々な音域や強弱で音を出し、自分の耳で確かめてみることをおすすめします。クリアで、長時間聴いていても疲れない音が理想です。
「最大同時発音数」は余裕をもって
これは、同時にいくつの音を鳴らせるかを示す数値です。例えば、和音を弾きながらダンパーペダル(後述)を踏むと、前の音が伸びている間に次の音を重ねていくことになります。このとき、同時発音数が少ないと、古い音から順に消えてしまい、音が途切れたり、響きが不自然になったりします。特にペダルを多用する曲や、音数の多い複雑な曲を弾く場合に影響が出ます。初心者の方でも最低「64音」は欲しいところですが、より快適な演奏のためには「128音」以上あると安心です。最近のエントリーモデルでも128音以上を備えるものが増えています。
4. ペダル – ピアノらしい響きを作るために
ピアノ演奏に欠かせない要素の一つがペダルです。特に、音を伸ばすダンパーペダル(サステインペダル)は、豊かな響きを作り出すために頻繁に使用します。
ダンパーペダル(サステインペダル)は必須アイテム
右端にあるこのペダルは、踏んでいる間、押した鍵盤の音を持続させる効果があります。これにより、音と音を滑らかにつないだり、豊かな響きを作り出したりすることができます。ピアノ曲の楽譜には、このペダルの使用指示が書かれていることがほとんどです。そのため、最低でもダンパーペダルを接続できる端子が付いているか、そして可能であればペダル自体が製品に付属しているかを確認しましょう。最初は付属の簡易的なスイッチタイプのペダルでも練習できます。
ペダルの質と種類もチェック
付属のペダルは、多くの場合、オン/オフのみを切り替える簡単なスイッチタイプです。これでも機能は果たしますが、アコースティックピアノのペダルは、踏み込みの深さによって音の伸び具合を微妙に調整できる「ハーフペダル」という表現が可能です。より本格的な演奏を目指す場合は、ピアノのペダルに近い形状と踏み心地を持ち、ハーフペダルに対応した別売りのペダルを用意するか、3本ペダル(ダンパー、ソフト、ソステヌート)が一体になった専用スタンドとセットで購入することを検討すると良いでしょう。ソフトペダルは音量を少し抑え、ソステヌートペダルは特定の音だけを伸ばす効果があります(使用頻度はダンパーペダルほど高くありません)。
5. 付加機能と予算 – 練習をサポートし、長く使うために
最後に、練習をより快適に進めたり、将来的な拡張性を考えたりする上で、付加機能や予算も考慮に入れるべき点です。
練習に役立つ基本機能
- ヘッドホン端子: 時間や場所を気にせず練習するために不可欠です。ほとんどのモデルに搭載されていますが、端子の位置(前面にあると抜き差ししやすい)や種類(標準プラグかミニプラグか)も確認しておくと、手持ちのヘッドホンが使えるか、変換プラグが必要かなどが分かり便利です。
- メトロノーム機能: 正確なテンポで弾く練習は、リズム感を養う上で非常に重要です。わざわざ別にメトロノームを用意しなくても、キーボード本体に内蔵されていれば、すぐに練習に取りかかれます。
- 録音機能: 自分の演奏を客観的に聴き返すことは、ミスタッチやリズムの乱れ、表現の癖などに気づき、改善していくための最良の方法の一つです。簡単なものでも録音機能が付いていると、練習の効率が格段に上がります。
拡張性と接続性
- USB端子など: 最近のモデルの多くは、USB端子を備えています。これにより、パソコンやタブレットと接続して、音楽制作ソフト(DAW)に演奏データを入力したり、ピアノ練習用のアプリと連携させたりすることが可能です。将来的に様々な使い方をしたいと考えているなら、どのような接続端子があるかを確認しておきましょう。
- スピーカーの有無と質 本体にスピーカーが内蔵されていれば、すぐに音を出して練習できます。スピーカーが内蔵されていないモデルの場合は、別途アンプ内蔵スピーカーやヘッドホンが必要になります。内蔵スピーカーの音質も、可能であればチェックしましょう。
- 予算とのバランス ピアノタッチキーボードの価格帯は幅広く、一般的に価格が上がるにつれて、鍵盤のタッチ感、ピアノ音源の質、スピーカーの性能などが向上する傾向にあります。安価なモデル(3万円台後半~)でも基本的な機能は備わっていますが、より本格的な練習や長期的な使用を考えるなら、最低でも4~5万円以上、できればもう少し予算を確保すると、より満足度の高い選択ができる可能性が高まります。ご自身の目標や練習環境、そして予算を総合的に考えて、最適なバランスのモデルを選びましょう。
ピアノ講師オススメのピアノタッチキーボード|電子ピアノ
88鍵盤

横幅が130センチほどありますが、できれば88鍵盤をオススメします。
YAMAHA(ヤマハ)P-145・P-225
P-145
P-225
CASIO(カシオ)Privia PX-S1100
ROLAND ( ローランド ) / FP-10
76鍵盤

初めはコンパクトなものから。という方は76鍵盤でもOK
NP-35
アコースティックピアノに近いオススメのサスティンペダル
ぜひ試奏を! – 百聞は一見に如かず、百見は一触に如かず
ここまで様々なチェックポイントを解説してきましたが、最終的に自分に合うかどうかを判断するには、やはり実際に楽器に触れてみることが一番です。
カタログスペックやレビューだけでは分からない、指先に伝わる鍵盤の重さや返り(キータッチ)、スピーカーから出る音の響きやヘッドホンで聴いたときの音質、ボタンや操作パネルの使いやすさなどを、ぜひご自身の感覚で確かめてください。
可能であれば、同じメーカーの異なる価格帯のモデルや、複数のメーカーの同価格帯のモデルを弾き比べてみると、それぞれの特徴や違いがよく分かります。楽器店の店員さんに、初心者であることや予算、探している機能などを伝えれば、的確なアドバイスをもらえることもあります。遠慮せずに相談してみましょう。
主なメーカーとその特徴
ピアノタッチキーボード(電子ピアノ含む)を選ぶ際に、よく名前の挙がる信頼性の高いメーカーをいくつかご紹介します。メーカーごとに音色やタッチ感に個性があるので、試奏の際の参考にしてください。
- YAMAHA(ヤマハ): 世界的なピアノメーカーであり、電子ピアノの分野でも長い歴史と実績があります。アコースティックピアノのノウハウを活かした自然なタッチと、クリアでバランスの取れた音色が特徴です。初心者向けからプロ向けまで、非常に幅広いラインナップを展開しています。
- KAWAI(カワイ): ヤマハと並ぶ日本の老舗ピアノメーカー。特に鍵盤のタッチ感に強いこだわりを持ち、木製鍵盤を採用したモデルなど、リアルな弾き心地を追求しています。深みのある落ち着いた音色が特徴とされることが多いです。
- Roland(ローランド): 日本が世界に誇る電子楽器メーカー。独自の音源技術(スーパーナチュラル・ピアノ音源など)による表現力の高さや、スタイリッシュなデザインが魅力です。デジタルならではの機能も豊富です。
- CASIO(カシオ): 電卓や時計でもお馴染みですが、電子ピアノの分野でも高い技術力を持っています。スリムでコンパクトなデザインや、コストパフォーマンスに優れたモデルが多く、初心者でも手に取りやすいラインナップが特徴です。
- KORG(コルグ): シンセサイザーや音楽制作機器で高い評価を得ているメーカー。電子ピアノにおいても、スタイリッシュなデザインと、ステージ映えするようなサウンド、そして比較的リーズナブルな価格帯のモデルを提供しています。
まとめ:自分に合った一台で、楽しいピアノライフを始めよう!
ピアノ初心者の方が後悔しないピアノタッチキーボードを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがありました。
特に「鍵盤のタッチ感」は、ピアノの弾き心地と上達に直結する最重要ポイントです。次に弾きたい曲を自由に弾くための「88鍵盤」、そして練習のモチベーションを保つ「心地よいピアノ音質」と十分な「同時発音数」が大切です。さらに、豊かな表現に不可欠な「ダンパーペダル」の有無や質、練習をサポートする「付加機能」と「予算」のバランスを考慮することが、最適な一台を見つける鍵となります。
カタログスペックだけでなく、可能であれば必ず試奏して、ご自身の指と耳で確かめることを強くおすすめします。
これらのポイントを踏まえ、あなたの目的や環境にぴったり合ったピアノタッチキーボードを選び、焦らず、楽しみながら、素敵なピアノライフへの第一歩を踏み出してください!応援しています。